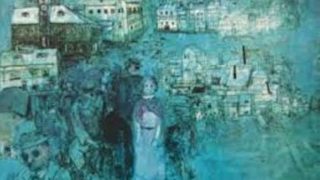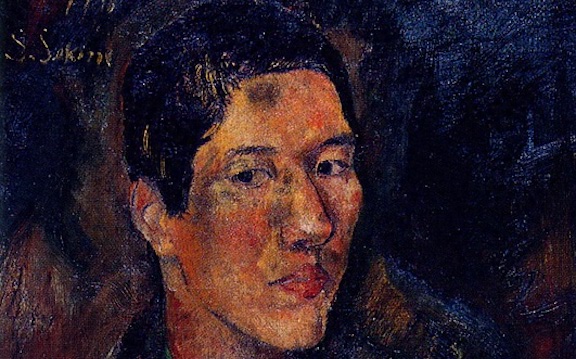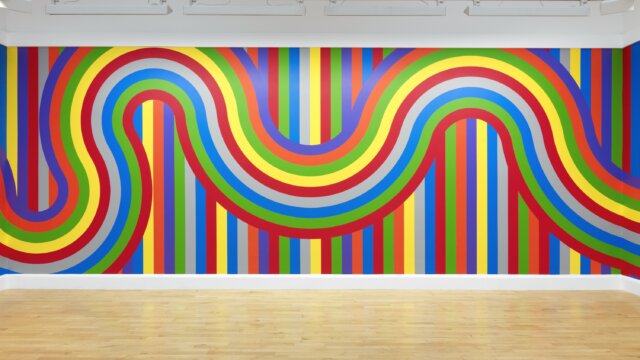日本洋画家の第一人者、相原求一郎。
川越市にうまれながら、多くの北海道の風景画を残し、作品は中札内美術館や川越市立美術館に収められています。
本記事では、相原求一郎の代表作品の解説、経歴、何故北海道の風景を描いたのか、またオススメ画集を紹介していきます。
相原求一郎のプロフィール、経歴

洋画家・相原求一朗は、1918年(大正7)に川越の農産物の卸問屋 父、茂吉、母、よしの間に生ました。
少年時代から絵を描くことを好んでいたようです。高校時代に美術教師から油絵を学んでいます。
1936年、川越商業学校を卒業し、東京美術学校に進学を志しますが、父親の逆鱗に触れ、家業を継ぎました。
美術学校に進むことはあきらめたものの、やがて独学で油絵を描きはじめます。
1940年徴兵により21歳からの5年間を満州(現中国東北部)やフィリピンで過ごし、帰還途中、搭乗していた飛行機が追撃を受け、重症を負って漂流しているところを、助けられます。
九死に一生を得て奇跡的に生還しましたが、この体験は作画への意欲をますます強めました。
1948年、猪熊弦一郎に師事。
1950年「白いビル」で新制作展初入選。
1961年、北海道に写生旅行に出かける。
満州での体験を甦らせ自身の原風景を発見します。北海道旅行で雄大な大地と風土に出会ったことをきっかけに自分の進むべき道を見出し、「具象」「抽象」という概念的な問題ではなく、自身の制作動機を大切にして、主に北の大地に取材した作品を発表するようになります。
1963年、「原野」「ノサップ」で第27回新制作協会展新作家賞受賞。
1968年、新制作協会会員になる。
1974年、第1回東京国際具象絵画ビエンナーレ招待出品。
1987年、埼玉文化賞受賞。
1996年、北海道河西郡中札内村の中札内美術村に相原求一朗美術館開館。
存命中に美術館が建てられたのは、喜ばしいことです。
相原求一郎美術館がある、中札内美術館について知りたい方はこちらもどうぞ
同年、川越市名誉市民になっています。
1999年、80歳で他界。
2002年、生地の川越市に求一朗が自作を寄贈した川越市立美術館が開館されました。
相原求一郎の代表作品
「路線のある風景」 1954年

作品からは、20世紀美術を代表する美術家のマチスやピカソの影響がうかがえ、家業を継ぎながら絵画制作をする相原にとって、時流に遅れまいとする意気込みが感じられます。
「原野」 1963年

第27回新制作協会展新作家賞受賞。
1961年の北海道旅行で自分の進むべき道を見出し、相原の芸術思考に転機を与えます。
北海道の展開する自然を「抽象」とみなし、そこから生まれる具象的な表現を追求していきました。
「すけそうだらの詩(ノサップ)」 1968年

彼の精力的な活動は海外の至るところに広きに及んでいます。
しかし中核は北海道、北フランス(ブルターニュ、ノルマンディー)が作品の主流となります。
「廃船のある風景」 1972 年

北フランスにての作品ですが、相原の「道」を描く特徴がここにも出ています。
厳しい寒さに耐えての港の姿と、そこに生きる人間模様とが、彼の詩的情が色の深さに現れています。
「斜里浅春 」1981年
1980年代に入ると、ライフワークとして、北の大地、北海道そのものを対象に、より精力的に制作を続けています。
ガッチリとして構成とマチエールで安定した世界が描かれています。
「天地静寂」 1994年

75歳を過ぎてからの大作。
90年代には、彼の創作意欲も盛んで、大作が多く残されています。
相原の絵画の総決算としての北海道にみる心の形がこうなったのであろうと思われます。
「風景画」というだけでなく、自然と対象しながら、人間の心情が織り交ぜられた心象風景画が、相原求一郎の世界であることは見えてきます。
相原求一郎のオススメ画集
相原求一朗画集 相原求一郎著 37999円
こちらは絶版で現在中古品しか手に入らないようですが、是非みたい一冊です。
 画家・相原求一朗の生涯 相原求一郎著 2160円
画家・相原求一朗の生涯 相原求一郎著 2160円
こちらは、画集ではありませんが、相原がどのように北海道を取材し、晩年まで絵を描き続けていたかが、記されている、相原求一郎を知るのはとても良いオススメの一冊です。
相原求一郎の絵画を展示してある「相原求一郎美術館」や「川越市立美術館」を訪れて実際の鑑賞できればいいのですが、時間の都合がつかない方には、オススメの本です。